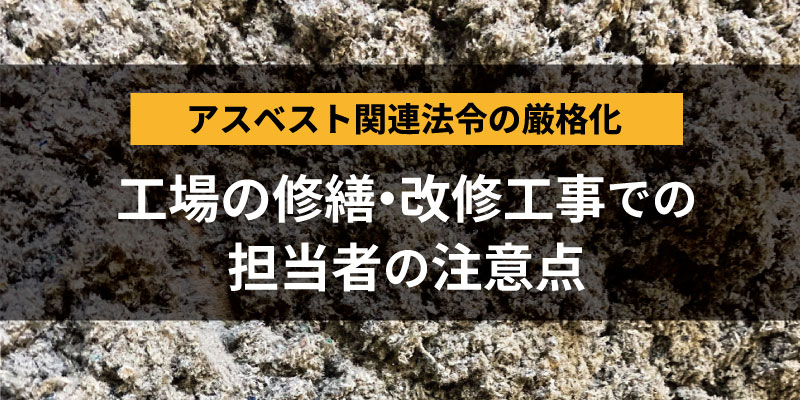2021年4月よりアスベストに関する法令が厳格化され、工場や倉庫などの建物を改修する際、「使用されている建材にアスベストが含まれているかどうか」の確認が義務付けられました。
法令の改正に伴い、どのような対応が必要なのかと不安に思われるご担当者様も多いと思います。
そこで本記事では、工場・倉庫の営繕担当の皆様に関わる
・アスベスト関連の法令改正の内容
・対応で気を付けるべきポイント
について解説をしていきます。
目次
法律改正の背景
まずは、法令が改正された背景から解説します。
アスベストは、安価なうえ使い勝手が良く、特に建材や摩擦材、断熱材といった分野の工業製品で重宝された材料でした。

上記写真のように、駐車場などで断熱材として壁一面に吹き付けられた※1アスベストはよく目にします。
アスベストは極めて細かく、非常に軽いため、建築物の解体・改修工事などの際に空気中に飛散します。
飛散したアスベストは人間の肺に入り込み、肺がんや肺線維症(じん肺)の原因になるため、現在では原則として製造・使用は禁止されています。
※1似た見た目の材料に「ロックウール」と呼ばれるものがあります。
「ロックウール」は石綿の使用が禁止された後に石綿の代替品として使われはじめた建材で、人体に害はないと言われています。
アスベスト関連の法律は、1960年に「じん肺法」として健康管理やアフターケアの仕組みが整備されてから、年々厳格化されています。
2005年に施行された「石綿障害予防規則」では、石綿を含む製品の生産が禁止され、石綿を含む建築物を解体する際のばく露防止措置が義務付けられました。
そして2021年、アスベストが含まれているか否かの事前調査を義務付ける「大気汚染防止法」の法改正が行われました。
石綿関連の法改正の履歴:
1960年 「じん肺法」の制定
1971年 「労働基準法特定化学物質等障害予防規則」(特化則)の制定
1972年 「労働安全衛生法」の制定
1989年 「大気汚染防止法」と関連施行令・規則の改定
1991年 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の改正
1999年 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」制定
2005年 「石綿障害予防規則」(石綿則)の制定
2021年 「大気汚染防止法」の法改正
引用元:石綿関係法規の変遷/千葉県
「大気汚染防止法」の改正内容
2021年に改正された「大気汚染防止法」の改正内容は、以下の通りです。
① 規制対象建材が「すべての石綿含有建材」に変更
石綿含有成型板(セメント等とともに成形された石綿含有建材)などから石綿が飛散した事例を受け、規制対象が「すべての石綿含有建材」となりました。
② 罰則の強化および、罰則対象が下請け事業者まで拡大
適切な処理なしで石綿が飛散する恐れのある作業を行った場合は、施工業者は罰則の対象となります。
罰則は元請け事業者だけでなく、実際に作業を行う下請け事業者にも、「作業基準遵守義務」が適用されます。
③ 事前調査の法定化※2
解体工事や改修工事を行う前の「事前調査」の方法が法定化されました。
調査は、「建築物石綿含有建材調査者」または「法施行前に日本アスベスト 調査診断協会に登録されている者」が行わなくてはなりません。
また、一定規模以上※3の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず元請業者等が調査結果を事前に都道府県などへ報告することが義務付けられました。
事前調査の記録は、工事終了後3年間する必要があります。
※2事前調査が不要なケースもあります。
※3規模要件は以下の通りです。
・建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
・建築物の改造・補修、工作物の解体・構造・補修:請負金額の合計が100万円以上
参考:環境省|リーフレット「大気汚染防止法が改正されました」
④ 作業記録の作成・保存
作業記録の作成、保存が義務付けられました。
さらに、工事業者は工事の発注者に作業結果の報告を行うことが義務付けられました。
工事発注者が気を付けるべきポイントは?
適切な調査・工事を行う業者を選定するために、営繕担当者(工事発注者)が気を付けるべきポイントは以下の3つです。
①建物に石綿含有建材が使われているかを事前に確認する

アスベスト含有調査を正確に行うためには発注者側の書面準備が欠かせません。
設計図・竣工図・改修図・対策工事記録などの設計図書や、製品仕様書を確認し、使用されている建材の製造年や製品名を確認します。
施工業者は、まずはこれらの書面をもって建材のアスベスト含有の有無を確認します。
製品名が分かる場合は、アスベスト含有の可能性のある建材を国土交通省の「石綿総合情報ポータルサイト」で調べることができます。
▼国土交通省 石綿(アスベスト)含有建材データベース
https://asbestos-database.jp/
②事前調査や飛散防止策を正しく行う業者を選ぶ
概算見積の段階で、以下2点を確認します。
・アスベスト調査費用が項目に含まれているか
・施工業者がアスベストの調査を行う資格を有しているか
例)アスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者
飛散防止を適切に実施する工事業者は、その分費用が嵩みますが、これは必要な対策費用となるため、概算見積段階で大まかな費用を確認しておきましょう。
③本見積書に石綿対策が記載されているか確認する
アスベスト調査後、本見積の段階で、石綿事前調査結果報告書の提出を求めましょう。
そのうえで、アスベスト飛散防止措置の明瞭な項目が記載されているかどうか確認を行います。
法令に則った工事の流れ
工事業者が石綿調査を実施する場合、以下のような流れで工事が進められます。

工事業者は工事対象物件の書面および実地調査を行い、石綿調査の結果を行政に報告します。
①書面調査
前章で解説のとおり、発注者が準備した図面などの書面を工事業者が確認し、石綿の有無を調査します。
参考書類をスムーズに工事業者に提示できるよう、事前に用意しておきましょう。
調査に利用できる書類:
・建物図面(平面図、立面図、矩計図、屋根伏図、建物配置図)
・建築確認書類(確認申請書、確認済証、検査済証)
・建物の仕様書(外部仕様書、内部仕様書)
・建物のパンフレット
※書類提出は必須ではありません。可能な範囲で準備を行いましょう。
②実地調査
実際に工事物件に工事業者が訪れ、建材に石綿が含まれているかを目視で調査します。
書面で確認できなかった箇所を細かく調査するほか、書面調査の内容に間違いがないかを確認します。
また、目視調査で石綿含有の有無が不明な場合、建材を採取して分析し、石綿の有無と種類を特定する場合もあり、別途調査費用が必要になります。
分析調査を省略できる「みなし工事」
工事業者によっては、石綿分析調査を省略する代わりに「みなし工事」を行う方法を採用している場合あります。
「みなし工事」とは、すべての建材が石綿を含有しているとみなして飛散防止措置をとりながら工事を進める方法です。
「みなし工事」により分析調査を省略することはできますが、書面調査・目視調査・調査悔過報告書の提出は省略することはできませんので注意してください。
③行政報告
工事業者が報告書を作成し、行政に提出します。
着工後は、調査結果に基づいて適切な措置が取られます。
まとめ
本記事では石綿関連法令の内容と工事発注者に求められる準備について解説しました。
適切な事前調査・工事を行う業者を選ぶために、本記事の内容を参考にしていただけますと幸いです。
工事費用や工期だけでなく、安全対策をしっかりと行える業者を選定することで、事故のリスクを低減させることができます。
ぜひ参考にされてください。
最後に
アステックペイントでは、工場・倉庫のスレート屋根・外壁改修工事をはじめとした各種外回り工事を承っております。
全国の工場・倉庫改修工事を得意とする有料認定施工店とのネットワークを活かして、安全対策に十分に配慮した高品質な塗装工事をご提供可能です。
まずは小さな工事やご相談からでも、お気軽にお問い合わせくださいませ。
無料ダウンロード資料もぜひご覧ください!
工場・倉庫の暑さ対策の検討に!遮熱データ資料