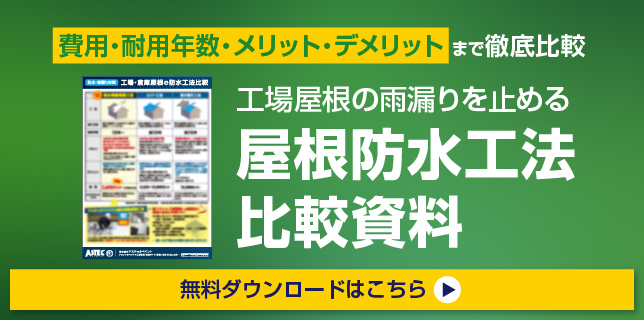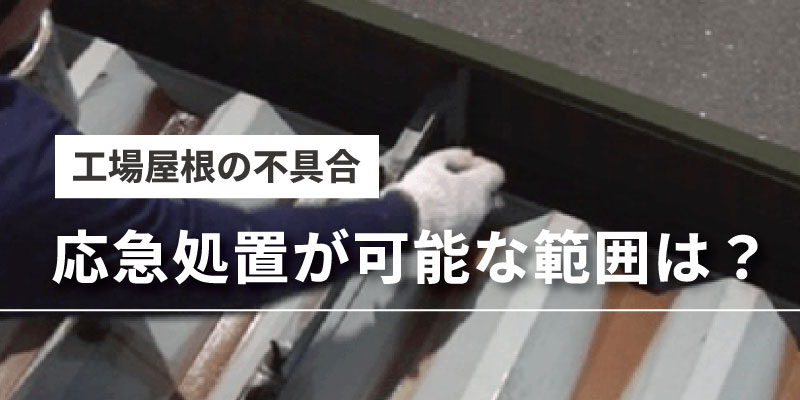工場や倉庫の屋根は、経年劣化や台風・強風などの天候の影響によって「破損」「雨漏り」が発生しやすく、対応が必要になる機会があるかと思います。
しかしながら、専門業者に相談せずに誤った応急処置を行うことで、後々の修繕の費用が嵩むなどのリスクもあります。
本記事では、工場・倉庫屋根の代表的な不具合症状について、「自社で応急対応できる場合」と「専門工事店に依頼すべき場合」の見極め方をご紹介します。
目次
「応急処置」と、専門業者による「修繕工事」の違い
応急処置とは?
応急処置とは、不具合が発生した際に、本格的な修繕工事を実施するまでの「一時的な対応策」を指します。
工場・倉庫の屋根では、雨漏りによる工場設備・製造製品などが被害に遭うのを防ぐため、
・防水テープやシーリング材で隙間や穴を一時的に塞ぐ
・ブルーシートで仮養生する
といった応急処置を施すことがあります。
このような応急処置は、不具合を根本から解決するものではありません。
使用する材料や応急処置の方法によっては、後日の補修工事や修繕工事に悪影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。
専門業者による「修繕工事」とは

一方、修繕工事とは、建屋や設備の劣化・損傷部分について、専門業者が本格的に補修を行う工事を指します。
例えば、工場・倉庫の屋根で雨漏りが起こっている場合、「屋根同士の接続部の浮き」や「明かり取り箇所のシーリング材の劣化」など不具合原因を特定し、機能を回復させることが目的です。
修繕工事には、
・屋根の塗装・カバー・葺き替えの工事
・防水処理(シーリング材・防水テープなど)の撤去・再施工
などの工事があり、一時的な応急対応に留まらず、長期的な視点で建物の機能を回復させることができます。
応急処置ができる範囲はどこまで?
よく見られる倉庫屋根・工場屋根の不具合症状および、営繕担当者で対応できる応急処置範囲と、専門業者に依頼すべき範囲を紹介します。
よく見られる倉庫屋根・工場屋根の症状
①屋根材の経年劣化

例)
・波形スレートのひび割れ・欠損
・折板屋根の屋根材同士のつなぎ目錆による孔食(穴あき)
などの要因から工場内へ雨水が浸入する。
② 防水処理材(シーリング材・防水テープなど)の経年劣化

例)
・明かり取りのポリカーボネート周囲のシーリング材が劣化し、隙間から雨水が浸入する
・工場屋根の接合部や補修部に貼られていた防水テープが、経年劣化によって剥がれ・硬化・粘着力低下を起こし、風雨時に剥がれた隙間から雨水が染み込むことで漏水が発生する
③屋根材の破損
例)
・台風や強風などによって、波形スレートや折板屋根に割れや破損が発生する
• 樋の経年劣化による割れや変形・詰まりなどによって、水が適切に排水されず溢れてしまう
・板金部分の錆びや変形、防水処理材(シーリング材など)の劣化によって、雨水が工場内へ浸入する
倉庫屋根・工場屋根では上記のような劣化症状が見受けられます。
応急処置が可能な範囲
本来は、屋根に上って応急処置を行うべきではありません。
屋根作業中の事故で最も多いのが転落事故で、プロであっても命の危険性を伴うためです。
そのため、必ず下記注意を守って、十分に安全に配慮してください。
【応急処置の注意事項】
・雨の日には上らない(足元が濡れていると滑落の危険性が非常に高い)
・2人以上で作業を行う
(1人は地上で待機し、梯子を使う際に支える等の補助、緊急時の連絡を行う)
・ヘルメットを着用する
・最低限の作業にとどめる
・原因が特定できない場合は無理に調査・修理せず、専門業者に任せる
・応急処置後は専門業者への修理を依頼する
・屋根材が波形スレート屋根の場合は上らない
※波形スレート屋根は踏み抜きによる墜落の危険性があるためです。
絶対に上らないようにしてください。
以上を踏まえたうえで、営繕担当者でも対応可能な応急処置例は以下の通りです。
• 金属屋根の接合部や隙間の簡易的な穴埋めとして、市販の防水テープやシーリング材を充填・貼付する。
• 明かり取り(トップライト)部分の隙間に外部用シーリング材や防水テープを充填・貼付する。※シリコーン系シーリング材は使用しない。
• 雨水の進入を防止するため、テープ・ブルーシートなどで仮養生する。
• 板金のずれをテープで一時固定する。
いずれも「一時しのぎ」の応急処置であり、速やかに専門業者による修繕工事が必要です。
【専門業者に依頼すべき修繕内容】
専門業者に依頼すべき修繕工事内容としては以下が挙げられます。
• 屋根に上って行う作業全般(特に明かり取り周辺の補修)
• 屋根からの雨漏りが止まらない、補修しても再発する場合
• 著しいシーリング材の劣化により、水が回っている可能性がある場合
• 屋根材の大きな破損や、広範囲な補修が必要なケース など
簡易的な作業で症状が改善しない場合や、適切な応急処置方法が分からない場合、または危険を伴う恐れがある場合は、速やかに専門業者へご依頼ください。
応急処置が招くリスク・注意点
応急処置そのものは、手近で手早くできる一方、不適切な処置により思わぬリスクや後々のトラブルを生み出すことも少なくありません。
代表的なリスクは以下の3点です。
補修材料の選定ミスにより次回の修繕・改修作業が難航するリスク
補修作業にシリコーン系シーリング材を使用した結果、塗替え工事時、シリコーン系シーリング材に含まれるシリコーンオイルにより
・塗替え塗膜の付着不良
・シミ上がりによる塗装面の汚染
が発生する可能性があります。
また、付着力の高すぎる接着剤や防水テープで補修した結果、改修工事時に
・材料の除去に時間や手間が増える
・ケレン作業で建材に傷がつく
といった可能性があります。
あくまで「応急」扱いであることに留意し、改修工事時の妨げにならない材料を選ぶことが重要です。
補修後に二次的トラブルが発生するリスク
応急処置で一部を塞いだことで、
・湿気や水がほかの箇所に回り、壁や天井に雨染みが発生した
・応急処置に使用した材料が劣化し、変色した
・浮いた外壁材をビス止めしたところ、ビスを打った箇所でひび割れが発生し、新たに水が浸入するようになった
など、想定していない二次的トラブルが発生する場合があります。
安全管理を怠ったことにより転落・墜落事故が発生するリスク
応急処置を急ぐあまり、
・墜落制止用器具(安全帯)などの装備をつけずに高所作業を始めてしまう
・老朽化した波形スレートの危険性を知らずに安易に屋根に上ってしまう
このような安全管理を怠った応急処置によって、作業中に転落・墜落してしまう可能性があります。
まとめ
応急処置はあくまで「最終的な改修を行うまでの一時的な対応」にとどめることが重要です。
現場での被害を最小限に抑えるため、以下の点を必ずお守りください。
・応急処置後は必ず、専門の改修業者へ相談し、正式な補修を依頼すること
・応急処置の際は、「今後の改修を妨げない」「除去しやすい」補修材を選ぶこと
・作業時には安全管理を徹底し、事故防止を心がけること
日々の営繕業務を安全かつ効率的に進めるためにも、本記事で「応急処置の限界」「リスク」「安全意識」を再確認し、現場事故・二次災害の防止にご活用いただけましたら幸いです。
対応に迷った場合や、特殊な材料が必要なケースは、必ず雨漏り補修の経験豊富な施工業者へ相談することをおすすめいたします。
関連のお役立ち資料はこちら